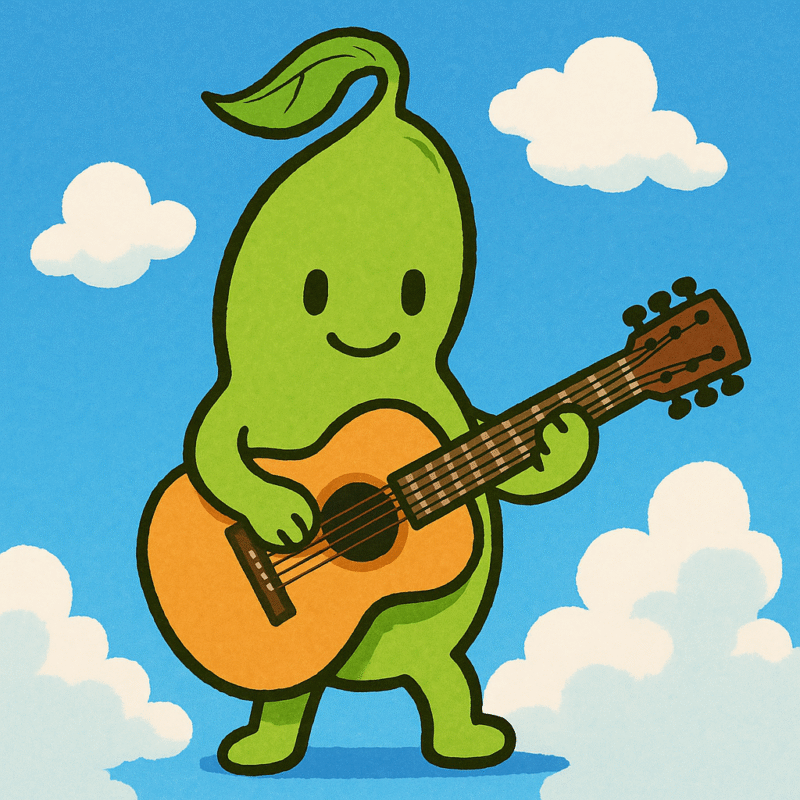はじめに
ここでは、南関東の気候を想定した枝豆の育て方を紹介します。
南関東は春の立ち上がりが早く、夏は高温・乾燥気味になるのが特徴です。そのため、種まき時期を分散させて長く楽しみ、雨不足のときは開花期に水分を確保するのが成功のポイントになります。
1. 土づくり
枝豆はマメ科なので、自ら根粒菌で窒素を作り出す力があります。したがって、窒素肥料は控えめにし、リン酸とカリウムを中心に土づくりをすると実つきが良くなります。
植え付けの2週間前までに苦土石灰をまき、30cmほど耕して土を整えておきます。
2. 種まき
南関東では4月下旬〜6月上旬が適期です。
一度に全部まくのではなく、3期くらいに分けて種まきするのがおすすめです。
4月下旬にまく → 初夏に収穫 5月中旬にまく → 真夏に収穫 6月上旬にまく → 盛夏〜お盆頃に収穫
こうすると一度に大量に実らず、食べきれない心配が減ります。また、天候不順で一度の収穫が不作になっても、次の播種でリカバリーできるというメリットがあります。結果的に、夏の間じゅう採れたての枝豆を楽しむことができます。
1か所に3〜4粒ずつまき、覆土をして軽く押さえ、水をたっぷり与えます。株間は30cm程度とりましょう。
3. 間引きと管理
発芽後、本葉が2〜3枚になったら元気な苗を2本残して間引きます。
生育初期は雑草に負けやすいので、草取りや土寄せをこまめに行います。
4. 肥料と水やり
開花前に追肥としてカリウム肥料を与えると、実入りがよくなります。
水やりは、特に開花期〜さやが膨らむ時期に欠かさないことが重要です。雨不足が続くと実が太らないので注意しましょう。
5. 品種の選び方
南関東では暑さに強く、実入りが良い品種がおすすめです。
湯あがり娘 … 甘みが強く、香りも良い定番品種。
あきた香り五葉 … 病気に強く、風味豊か。
サッポロミドリ … 粒が大きめで収穫の満足感が高い。
6. 収穫
種まきから70日〜90日ほどで収穫期を迎えます。
さやの表面にうぶ毛が立ち、実がふっくらと膨らんできたら収穫適期です。とり遅れると実が硬くなり風味も落ちるので、タイミングが大切です。
7. 食べ方と保存
収穫した枝豆は時間がたつほど風味が落ちるので、できるだけ早く調理します。塩ゆでが定番ですが、炒め物や混ぜご飯に使うのもおすすめです。
余った場合はさやごと冷凍保存できます。食べたいときに凍ったまま塩ゆでにすれば、風味がかなり残ります。
ワンポイント
雨が少ない年は「開花期に1度でも雨が降るか」が豊作の分かれ道。
連作は避け、3〜4年は間を空けて育てると病気を防げます。
収穫したてをすぐに食べるのが枝豆の醍醐味。
種まきを3期に分けることで、夏を通して枝豆を楽しめ、天候リスクの分散にもつながります。